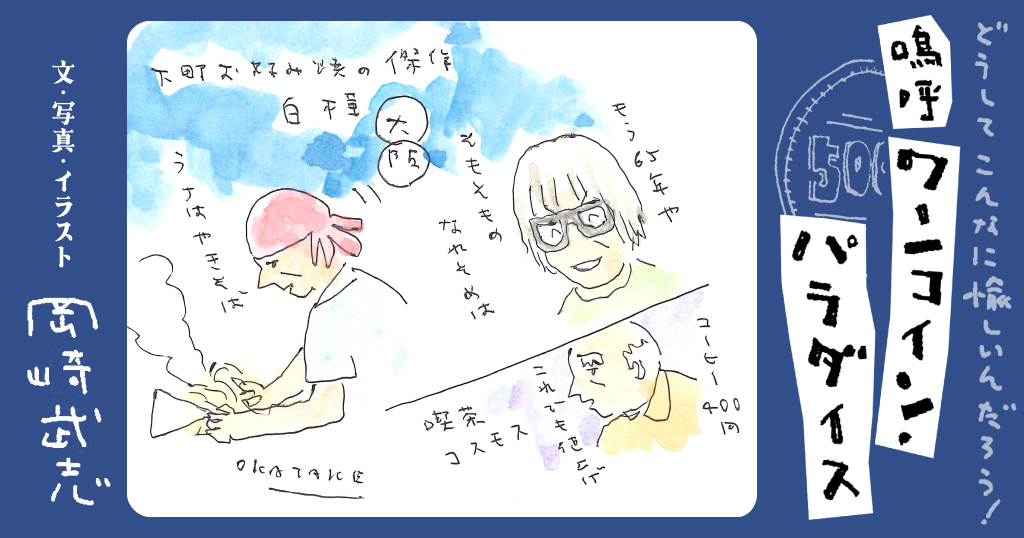私は発信はしないが「X」に登録してあって、日々情報が更新されていく。九割はくだらない政治批判や、アクセス数を上げるためだけの暴力的な動画などが蔓延し、うんざりすることのほうが多い。フォローしているのは知人か、古本屋関連だけなのだが、どういうわけか不穏な情報や動画が侵犯してくる。
そんななか、本好きの間で話題沸騰となったのが、『週刊現代』のウェブ版「現代ジャーナル」(10月15日)にアップされた記事。「約2万冊の大半が『ゴミ』に……知の怪人荒俣宏が蔵書を処分して感じたこと」だ。もう少し読むと、いわゆる終活による決断で、一軒家からマンションに引っ越したこと、大きな病気をしたことを契機に処分を決意した。残したのは500冊というから極端だ。荒俣宏さんは1947年生まれで、今年78歳。
記事によれば、稀覯書など約1万冊を付き合いのある海外の古書業者への買い取りと、役員を務める「角川武蔵野ミュージアム」へ寄贈したという。ここまでは問題ない。本好きを刺激したのは、「70年かけて蒐集した貴重な稀覯本ですら、『ゴミ』になってしまった」という点。産廃業者がトラックで運んだというのもショックだった。
これに反応した人のコメントを読むと、「ゴミ」になった1万冊を古書業者がどうにかできなかったのか、ひどいじゃないかという意見が一つ。ほかに、すかさず古書業者がツイートして、しかるべき業者に手渡せばもう少し本が生かせたという声。
具体的なことはわからないまま、どうこう言うのは部外者として僭越なのだが、なにしろ、あの荒俣宏さんが持っていた本が「ゴミ」というのがやりきれない気持ちにさせられる。本当にほかに方法はなかったのか。
私はこれまで蔵書を何度も大量処分した経験があり、知人の古書業者にくっついて買い取りの現場も知っている。じつは、一般家庭から出た本は、よほどの希少本や出てまもない新刊以外はほとんど値がつかないのが現状だ。ネットの普及で本を読まない人の大量発生と、本が売れない情勢は、本そのものを大きな不良在庫にしてしまっている。残念ながら。
荒俣さんは『稀書自慢 紙の極楽』(中央公論社・1991年)という古書に関する立派な本を出していて、洋書のアートブックスや図鑑を中心に、ため息が出るような美しいコレクションを開陳している。さすがにこれらは「ゴミ」になることはなかっただろう。考えるに、荒俣さんほど多方面の執筆活動をしている人なら、歴史書や一般書、あるいはマンガを含めて雑多な蔵書を抱えていたはずだ。正直言って、それらのうち値がつくのはほんの一部。
それだけではない。さる情報筋から聞いた話でニュースソースは明かせないが、荒俣さんだって、自分の蔵書の価値がわからないまま「ゴミ」に出したわけではなさそうなのだ。あれだけ若き日より古書店と付き合い、古書まみれの人生を送った人が「ゴミ」の中から値がつきそうな本を選別するのはたやすかっただろう。

ゴミになるのは必然だったか
じつは、処分された本を見た人がいて、それらの多くは図版やページの切り取りがあったという。本を執筆の道具と割り切って、必要なページなどを切り取り、別にスクラップしていたようなのである。どんなに貴重な本であっても、切り取りがあれば価値はゼロである。「ゴミ」になるのも致し方ない。だから、別の古書業者が取り扱っていれば、処分の仕方も変わっていただろうという説は成り立たない。誰がやっても結果は同じだったろう。
長年の本との付き合いは、とくに文筆業者にとってあまりに関係が濃く、ほとんど肉体の一部になっている。それを失うことは、ほんの少し「死」に近いできごとだ。短い談話だけからは、本当のところはわからないけど、荒俣さんにとって大量蔵書処分は痛いには痛かっただろうが、何もかも承知のうえでの決断だったと思う。どんな本を500冊残したのかは気になるが、私にはある種、すがすがしい行為に見えた。
本を売る際の要諦は、お金になる(利殖)ことを考えないほうがいい、ということ。たとえ読んでいなくても買った時点で、売価分の対価は得ている。本はそのままの形で残るのがやっかいだが(それが利点でもある)、食べ物なら腹に消えてしまう。食べた後で料金を返せという人はいないだろう。処分して、値のつくものは店やネットで売られて、また別の人の手に渡る。それは素敵なことではないか。
本は100年前のものでも楽々読むことができる。優良なリサイクル商品なのである。還暦になったら、一度、部屋を圧する本をすべて処分してしまう、というのも一つの手だ。また、読みたくなったら図書館で借りるなり、古本屋やネットで買えばいいのだ。ごく普通の一般家庭に置かれている本の量は500冊でも多く、1000冊なら「この家はたくさん本がありますね」と言われるレベルだ。処分は簡単である。
さらにもう一つ申し添えれば、今回の荒俣さんの1万冊は産廃業者が扱ったというが、地域のゴミの日に出す本は、古紙回収業者の集積所(建場[たてば]という)に行く。業者に話を聞いたことがあるが、そこでは本や雑誌は別に取りのけておくそうだ。それらは古書業者が定期的に買いに来る。ゴミとして出しても、断裁焼却されず、また世の中へ戻っていく。
荒俣さんの事例から、いろんなことが見えてくる。
大阪でチンチン電車で小旅行
甥の結婚式に出席するため、久しぶりに京都へ帰省した。京都には一人暮らしの母親や、弟妹が一家を構えて住んでいる。日帰りは無理でも、1泊2日でじゅうぶん事は足りたが、日を延ばして、この際だからあちこちへ行くことにした。
京都駅に着いた一日目は琵琶湖に近い寺町の坂本へ。二日目は結婚式当日で、式場に近い清水寺周辺を歩いてみた。滋賀にも京都にも長く住んでいたのだが、坂本へは初めて、清水寺も訪れたのはずいぶん昔、一回きりだ。そして結婚式出席を済ませた翌日の三日目には大阪へ。ちょうど大阪の実家へ帰ってきている、散歩の相棒Мさんを誘って、阪堺[はんかい]電車の半日散歩を楽しんだ。
大阪市南部から堺市を結ぶ路面電車で1911年の開業。正式には「阪堺電気軌道阪堺線」と呼ぶらしいが、地元では「チンチン電車」がもっぱらの呼び名。専用軌道も走るが、一部、自動車も行き来する道路を一緒に使用する。オリンピックの短距離選手なら抜けそうなスピードで、生活感のある街中を走るのが見どころ。


今回、一日乗車券(700円)を買い、二ヵ所で下車するつもりだった。最初は住吉大社。大阪を代表する巨大な神社である。地元では「すみよっさん」。私は小学校低学年の時、近くに住んでいる叔母を訪ね、そのとき住吉大社へお参りしている。ただ、途中の池にかかる「反橋[そりばし]」という高さ3.6メートルの太鼓橋を怖くて渡れなかった。記憶しているのはそれだけ。
この日は大嘗祭に七五三が重なって大変な人出だ。太鼓橋を今度はわたり、行列の本宮(一~四まである)の参拝もスルーして、脇へ逃れて「住吉の長屋」へ。今や世界的な建築家である安藤忠雄の初期代表作として有名な、コンクリート打ちっぱなしの民家がある。これを見たかった。三軒長屋の真ん中の家を建て替えるとき、指名されたのがまだ無名だった安藤。当時新しかったコンクリートむき出しの、前面から見ればほぼ四角の建物で1976年竣工というから、もう半世紀経つ。屋根なしの中庭は、雨の日は傘をさして移動するなどの不便(冬は寒い)がありながら注目され、安藤の名を一躍高めた。写真をパチリと撮って満足。


「白樺」から「コスモス」へ黄金のコース
お昼は、事前に目をつけていた粉浜商店街近くのお好み焼き屋「白樺」へ。ここが素晴らしい店だった。L字型の鉄板を敷いたカウンターのみの客席でキャパは10名程度。我々が行ったときは満席で「10分待ってもらったら」と言われ、まさしく10分後に入店。後ろに並んでいた家族づれに「ここ、おいしいですか?」と聞くと「このあたりでは一番だと思います」。期待は高まり背中を後押しする。
ブタ玉2枚にやきそば、それにビールを1本注文する。お好み焼きはもちろんおいしかったのだが、この店の良さは六十代らしき店主夫婦の掛け合い、コンビネーションにある。白髪のきれいな奥さんは、やや漫才の大助花子の花子が入っていて、よくしゃべり明るい。「こないだ三姉妹で映画観てな」「うちの亭主とのなれそめは、やな」などトーク全開でそれが嫌味でない。お客をくつろがせ、居心地のいい空気を作っている。
ここは青のり、かつお節をかけない式らしく、それを知らずにやきそばが運ばれてしばらく待っていたら亭主が「はよ食べんと焦げるよ」。するとすかさず奥さんが「ちょっと焦げたほうがおいしいけどな」とフォローする。これだけの人気店でありながら、店内にタレントの色紙などが飾っていない。「宣伝なんかしてもらわんかって、うちにはお客さんがついている」という自負であろう。大阪のお好み焼きの名店数々あれど、私はここをベストとする。

「白樺」からすぐそばの粉浜商店街はアーケードの商店街で「すみよっさん」のおひざ元。雑貨店や古道具屋、その他、すぐには何を主力とするのか判別しがたい不思議な店が並ぶ。そのなかに「コスモス」という古い純喫茶を見つけ入った。「白樺」から「コスモス」というと、大正昭和初期の文芸同人誌みたいなネーミングだ。表の値段表を見ると、コーヒー400円。値段が張り替えてあって、あとで検索するとつい数年前までは350円だった。
民芸調というより自然に古びた店構えと店内は「レトロ」と呼ぶのは語弊あり。ただただ時間の経過でこうなった、という店だった。九十歳にはなろうかという男性店主のワンオペ。客はほかに一人。「コーヒー2つ」と注文すると「ちょっと待ってもらわんと」と言う。「いつまでも待ちます。明日、と言われると困るけど」と大阪人らしい会話を。
本当に「ちょっと待って」から店主がテーブルへ来て「なに、しましょう?」と来た。(いや、さっきコーヒー2つと言いました)の声は飲み込み「コーヒー2つ」と改めて注文する。ドンマイ、ドンマイ、これかて大阪の味やおまへんか。コーヒーはちゃんとサイフォンで淹れて、カップになみなみと注がれておいしかった。それまでの経緯と安さから、コーヒーの味はうんぬんするものではないかと疑ったが、いやあ、ちゃんとした味でした。
すっかり気持ちがほどけ、コーヒーを飲み干し店を出ようとすると、店主がカウンターから出てきて「ご主人、お聞きしたいことがあるんですけど」と言うではないか。何を聞かれるかと身構えていたら、さっきまで女性客が座っていた4人席の椅子を指さし、「いつもあの女性が座った後、シートに小さく凹んだ跡がつく。これ、いったい何でしょう?」と聞くのだ。「なんでしょう」と言われても、ホームズじゃないからな。「かの女性は五十代、阿倍野から住吉大社へお参りにきて、近くの友人宅を訪れた後、この店へ……」などとわかるわけもない。しかし、何か答えたいではないか。
「おそらくですが、女性が履いていたジーパンの尻ポケットに鋲がついていて、その跡ではないですか」と推理した。すると店主が「なるほど、そうですか」とえらく感心された。店名の「コスモス」は花の名ではなく、宇宙を指すのかもしれない。「白樺」から「コスモス」へ。大満足の飲食コースであった。


タイトルイラスト、写真=筆者

おかざき・たけし 1957年大阪生まれ。立命館大学卒業後、高校の国語教師、出版社勤務を経てフリーライターに。「神保町ライター」の異名を持つ。近著に『憧れの住む東京へ』(本の雑誌社、2023年)、『古本大全』(ちくま文庫、2024年)、『ふくらむ読書』(春陽堂書店、2024年)などがある。